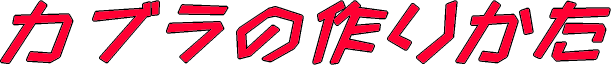 |
 |
| 用意する材料 |
| ① カブラ用の親針 |
③ カブラおもり |
|
④ まご針 |
② ちめ糸
3本撚りと12本撚り
太さの違う2種類使います |
⑤フロロ10号
⑥フロロ6号 |
|
 |
親針にはテンヤ用のものとカブラ用のものがあり
それぞれ、糸を結んだときの抜けどめの突起が
左のように針の曲がりに対して直角なもの(テンヤ用)
右のように曲がりと同じ方向(カブラ用)があります。
オモリをたたく時に影響しますので、必ずそれにあった
親針を用意しましょう。 |
 |
まず、オモリの半分あたりまで割り込みを
のばします。広げるのには、ノミのようなものを
使うと簡単にできますが、あまり広げすぎると
親針を固定するときにやりにくくなります。
できれば、親針の2倍程度の広さに
広げておきたいです。
このとき、左右がキチンと対称になるように
割り込みを広げないと、バランスよく作れません。
新太郎カブラのように、最初から
割り込みが深く入っているものもあります。 |
|
 |
孫針を結ぶための輪を作ります。
フロロの10号が張りがあってまっすぐになるので
最適です。
結び目は下の図のように結びます |
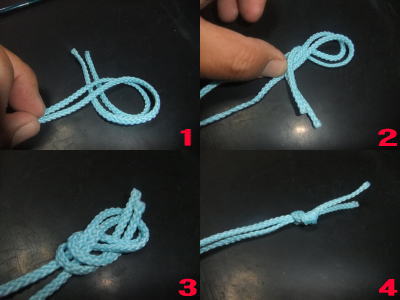 |
1、糸を下からまわし
2、上の輪の中に下から通します
3、 8の字ができます
4、 締めこんでできあがり |
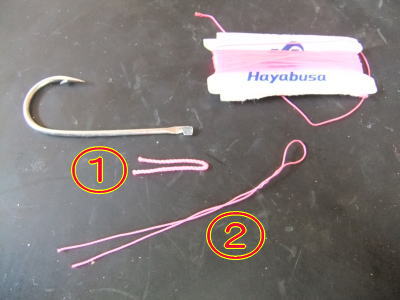 |
親針に12本撚りのちめ糸をしばります。
2つ折にしたちめ糸を3本撚りの糸でしめます。
① 12本撚りを二つ折り
② 3本撚りを2つ折、これは、あとで糸を
絞めるのに使います
|
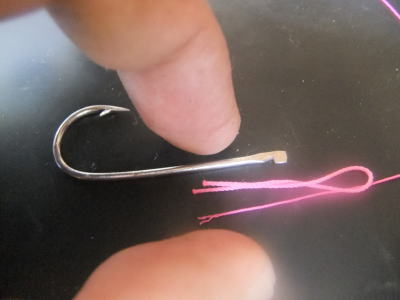 |
親針に①の12本撚りの二つ折りと3本撚りを
位置を合わせてつかみます |
 |
針のちもと(右のほうの段がついたところ)から
3本撚りを巻きつけていきます。 |
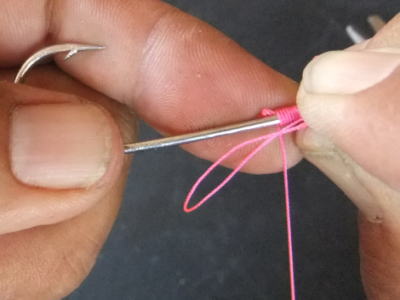 |
残り5巻きくらいを残して、②の3本撚りの2つ折の
ものをいっしょに巻き込んでいきます。 |
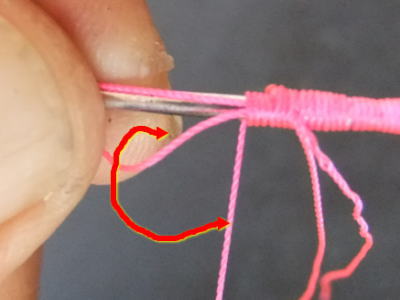 |
巻き込み終わったら、3本撚りの糸を切り、
2つ折の輪の中を通しておきます。 |
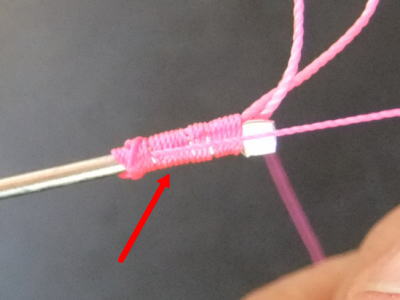 |
2つ折の3本撚りを引き抜きます。すると、巻きつけた
糸の下から3本撚りの糸が出てきます。
余った部分を切るとほつれることもなく
きれいにできます。
心配なら巻きつけた部分に
瞬間接着剤を少しつけてください。
|
 |
出来上がりです。 |
|
 |
かぶらの割り込みに孫針用の輪を下に、その上に
親針を入れます |
 |
横からかぶらの親針に向かって少しづつ
たたき、つぶしていきます。
針が真上に向くように確認しながら
たたいていきます。 |
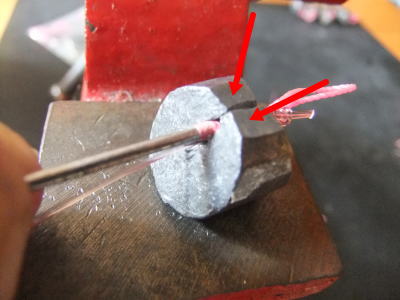 |
ある程度針が固定されたら今度は上の左右から
絞めこむようにたたきます。このときにあまり
強くたたかないよう。上が平らになりすぎます。 |
 |
角をつぶすようにしながら、形を作っていきます。
後ろから見てハート型になるのが理想です。 |
 |
カブラはつるしたときに8時の方向を向くくらいが
一番食いがいいです。
この角度を決めるのは
割り込みに針を入れる深さで決まってきます。
浅いほうが針は寝ます。(9時)
深いと立ちます。(6時) |
|
 |
孫針を結びます。
|
 |
孫針のダブルラインの結び方です。 |
|
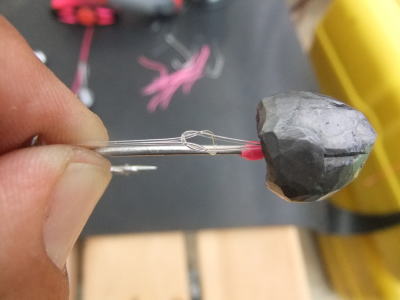 |
できあがった輪をカブラの輪に通します。
|
 |
エビのおおきさにかかわらず
孫針の糸がたるまずにきれいにつけられます。 |
 |
完成形です。 |